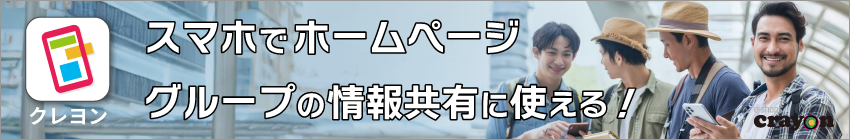このHPは生活の発見会公認のホームページではありません。
また。集談会のホームページでもありません。
あくまで私、真之介(しんのすけ)個人の非公式ホームページです。
以下の内容は生活の発見会のベテラン会員、集談会の幹事クラスを対象にして、私の考えを述べたものです。森田初心者の方や集談会への出席回数の少ない方などには向かない内容です。
理論学習はどこまで必要か?
2022年に「理論学習はどこまで必要か」という表題の文章を発見誌に投稿しました。その原稿は表題を変え、中身も少し変更されて2023年の発見誌に掲載されました。評価は概ね良かったと思います。
発見会本部から9名の方の感想文が寄せられましたが「やはり理論学習は必要だ」という反対意見は1名のみ。他の方からの評価は高いものがありました。以下はそのうちの一部です。
〇 今までにない斬新な森田の解説書だと思います。改めて、五巻を読んでみようと思いました。かなりの期間、習熟されていなければ、こういう文章は書けないと思います。
〇 「おー、私が言いたかったことが、記事になっている」と感じました。
この記事では、冒頭に森田療法の専門家である久保田幹子さんの言葉を紹介しています。
あんまり「学習しましょう」っていう路線にしすぎない方が「本当の森田」のような気がするんですよね。最終的には学習から抜けるのが、本当の森田のような気がするんですよ。
(発見誌2020年2月号、前理事長との対談記事より)
この久保田先生の言葉は、私が昔から何となく感じていたことを見事に言葉で表現されている、と思ったものでした。久保田幹子さんに係わらず、多くの専門家の人達が発見会方式での「理論や言葉にこだわる事」に否定的見解を述べています。(例えば発見誌2024年11月号の中村敬先生へのインタビュー記事P62~では、中村先生は発見会に遠慮して慎重に言葉を選びつつも、理論に偏ることに対しやや批判的です。)
私の発見誌掲載文にも以下の森田先生の言葉を引用していました。
理論は実際に是非必要のように考えてそれからそれへと進むと、ますます実際から遠ざかって行くことを忘れてはならない。(『森田正馬全集第五巻』P92)
知識ある人が治りにくいのは、実行が伴わぬからで、(中略)時に不用の知識は捨てることが大切。(P162)
「生の欲望」とか「善悪」とかの文句・抽象をやめねばならぬ。言葉の詮索・理屈での研究はいけない。(P334)
僕の考え方(森田理論)は、ご承知のこどく、常に実際と実行とを主眼としているから、あまりくどい説明を好まない。(P227)
ここで勘違いして欲しくないのは、私は理論学習が全く必要ないなどと思った事は一度もないということなのです。ただ「理論偏重」は望ましくないと言っているだけなのです。久保田幹子さんの言葉を借りるなら「最終的には」学習から抜けるのが本当の森田のような気がする、ということなのです。同時に2024年11月号の中村敬先生の意見は、本を読んだだけで(理論を学んだだけで)症状が軽快するような症状の軽い人はともかくとして、症状が本当に重い人に対しては理論はあまり役立たないという趣旨のようです。
集談会に出席するような人は、どちらかと言えば比較的症状の軽い人なので、理論学習はそれなりに有効だと私も思います。しかし理論にとらわれ、言葉尻にとらわれ始めると、学習がむしろ害になることさえある、と私は体験上そう思ってもいます。
以前の発見誌(比較的最近の号だったと思います)で、ベテラン会員が自分の人生を振り返る体験記のような記事で、症状が重かった頃に基準型学習会を5回受講したが、症状は軽快しなかったという記述がありました。つまり「理論さえ学べば症状は軽快する」とは限らないのです。
森田正馬が「まだこの患者に理論を説くのは早い」と語る記述が全集五巻にありました。患者が「頭でっかちになる」ことを防ぐためのようです。症状がある程度軽快した後で、再発防止の意味合いで理論的な事を教えるのが、森田先生流のやり方だったようです。
しかし発見会ではそうもいきません。なぜなら森田先生は患者を自分の自宅に住まわせて、家族のようにして「再教育」する方式だったのに対し、発見会ではそういう方法は不可能だからです。たから、発見会では理論から先に入るしか方法はないのです。私はそこまで否定している訳ではありません。
このブログでもそうなのですが、私の文章は森田正馬やその他の専門家の人達の意見を結構沢山引用しています。それは、ひとつには自分の言葉だけで的確に語れる自信がいまひとつないからでもあります。それから昔から私の事を直接知っている人は「あいつがまた変な意見を言い始めたぞ」と思うに違いないと予測して、「私の意見ではない。森田正馬の意見なのだ」と「虎の威を借りる狐」的な主張を意識的に展開しているからでもあります。
にも係わらず私が驚かされたのは、「発見会は森田理論を学習する場なのに、理論学習は必要ないとは何を言ってるのか」という意見が、身近な人達の間では一定数あった事です。
専門家や森田正馬自身が言っているのに、なおかつ自分の意見の方が正しいと言うのだろうか?と私は驚いたのです。森田療法の創始者である森田正馬が何と言おうが、自分の意見の方が正しい、そう思える頑迷さには驚きました。と同時に、何を言っても通じない人には通じないものなのか、という無力感を痛切に感じました。いやはや、人の心を変えることは出来ないものです。
私が期待したのは「あなたの言う通りだ」という全面的な賛成ではなく、「なるほど、森田先生はそんな事を言っていたのだな。ならば自分も全集五巻を読んで少し考えてみようか」という姿勢だったのですが。
参考までに・・・以下は発見誌掲載文には書かなかった、全集五巻の森田の言葉の引用です。
これは決して理論で治すのではない。ちょっとした心のはずみであって、つまり「コツ」であるから、実行しなければ、決してわかるものではありません。(p76)
理屈を知れば知るほど、実行から遠ざかり、悟りから離れるようになるかと思う。(中略)単に説明のための説明、理論のための理論に堕して、自分の当面の心境その物の表現ではないのである。(p506)
言葉というものは、我々の心を完全に言い表す事の出来ないものであるから、言葉尻の議論は、あまり役に立ちません。 (中略)言葉のはしにとらわれ、「物そのものにならなければいけない」とか、その考えに自分が支配されている間はだめです。(p616)
【元患者である井上氏(井上常七さん?)の発言】理論と実際との間には、あまりにはなはだしい隔たりがある。少なくとも神経質は、理論では救われない。(p120)
【元患者である中島氏の発言】私は入院中に、先生のお話を感じで聴かず、いたずらに理論家してしまったという事が、大いなる間違いでありました。(中略)実行の伴わない理論はことごとく間違いの元になります。(p120)
「発見会は理論を学ぶところだ」などと言う既成概念ではなく、もっと論理的な反対意見であるならば、私ももっと素直に耳を傾けたいと思っています。例えば「あなたは全集五巻〇〇ページの森田先生のこの言葉を引用しているが、森田先生はそのような意味合いで言っている訳ではない。それに〇〇ページでは森田先生は理論を学ぶ事は是非必要な事だ、と言っているではないか」などと言う反論ならば、私もなるほど、と思うのかも知れません。(とは言いつつ、それもまた水掛け論になって言葉の応酬となり、ひいては「言葉へのとらわれ」になってしまいそうですね。いやはや です。)
アドバイスの問題 その1
森田正馬が患者達に助言(アドバイス)する内容は、人によって全く正反対の事を言うこともありました。また同じ人に対しても時と場合により全く正反対の事を指示したりもしていました。この患者に対してはこう言った方が良いが、こちらの患者に対しては、逆にこう言った方が良いようだ、と使い分けていたようです。相手の症状の程度や状況を見極め、見定めて、アドバイス内容を変えていたのです。
『森田正馬全集第五巻』などの森田の原著を初心者が読む場合に「森田先生はこのページではこう言っているのに、別のページでは全く真逆の事を言っている」と混乱する事が多い、とは昔からよく言われることです。
森田正馬自身の以下の説明でも、そのような事が理解できると思います。
「人を見て法を説け」といって、誰でもかでも、同様の言葉や手段でもって押し通すのではないという事であります。(中略) (患者の)気質によって、その説法の仕方が違わなければならぬ。(森田正馬全集第五巻P510)
形外会(発見会で言う集談会)の出席者が、仕事で疲れた時には休養するべきか、それとも無理をしてでももっと働くべきか? こんな時どうすれば良いか、と質問します。以下はそれに対する森田先生のコメントです。
どうも神経質の人は、判断が窮屈でいけない。物の見方が一面的・独断的である。つまり早く一定の判断をして解決し片付けようとするからでもあろうか(中略)
また我々の仕事なり、能率なり、すべての行為について、神経質は、これを最も自分の都合のよいように、公式にあてはめ、一定の標準を立てようとする。まことに便利であるようであるけれど、世の中の事は決してそんな単純なものではない。(中略)
「疲労した時は、休息すべきか、もっと働いてもよいか」などいう問答も、みな同様の理想主義の型にはまったものである。((中略) 決してあらかじめ公式をもって定めておくことはできない。(中略) 決して一律にいう事はできない。 全集五巻P575
この場合、森田正馬が言いたかったのは、どんなに疲れていても無理をして仕事をせねばならない時もあるし、逆に休息しても良い場合もある。それはケースバイケースである、という事のようです。
ところが、もし集談会で森田先生のような返答をすれば、何だかはぐらかされ、煙に巻かれたような感じを受けるかも知れません。従って、生活の発見会では質問をした人の状況を詳しく聞き出して、「休息した方が良いのでは」とか一定の回答をするのかも知れません。
しかしそれは、相手から「どうすれば良いのでしょうか?」などと質問を受けた場合だと思います。
発見会のベテラン会員のなかには、そのような「ケースバイケース」の事柄に対して、やたら「こうした方が良い」と断定的に言う人がいます。質問された訳でもないのにアドバイスする人もいます。
またそのような断定的なアドバイスの方が、森田先生のような返答よりも遥かに「ウケが良い」のです。
質問する方も、アドバイスする方も、「どちらもどちら」なのだと私は思うのです。
どちらの側も「型にはまった公式」が好きなのです。質問する人もそれを求めているし、回答するベテラン会員も、元々神経質性格なので「型にはまった公式」が好きなのです。
私がその事に気づかされたのは、森田正馬の以下の言葉に出会ってからです。
「性格の違う人とは交際ができない」(どうすれば良いか)とかいうような質問は、典型的な神経質の特徴であって、神経質でない人は、ほとんどこのような質問はしない。
(中略)神経質は自己中心的な功利主義から、自分の苦痛を最も少なくして、最も大なる幸福を得ようとする工夫から、楽々と愉快に人と交際し、何事にも自分の思い通りにしたいと考えるからであります。(全集五巻P571)
つまり、「どうすれば性格の違う人と交際が出来るようになれるのか?」という質問をするのは「こうすれば、そうなる」という「型にはまった公式」のような回答を求めているからです。森田正馬はそれを見抜いて批判していましたが、発見会では「こうすれば良い」というウケの良い回答をせざるを得ないのかも知れません。それに、回答するベテラン会員も「型にはまった公式」が実は大好きなのです。(「学習の要点」が重宝されるのも同じ理由かも?)
同じような内容の質問を受ければ、誰に対しても、どんな場合でも、概ね同じようなアドバイスをするベテラン会員もいます。
単純な見方をすれば「一貫性がある」と評価する人もいるのかも知れません。
しかしそれは、森田正馬の言う「型にはまった公式」がそのベテラン会員の中にあって、それを誰に対しても当てはめようとしているだけなのかも知れないのです。
それに、人の悩みというものは、人それぞれに違うのです。似たような悩みではあっても微妙に違っているはずです。それを同じアドバイスで一刀両断するのはどうなのでしょうか。
そのような「アドバイス好きなベテラン会員」には、以下の二つのタイプが存在すると私は感じています。
知識主義の人
森田の本を沢山読み、学習会なども受講して、森田理論に一定程度詳しい人。あるいは森田でなくともメンタルヘルスの勉強をした人で、知識が豊富な人。
このタイプの人は、知らず知らずのうちに自分の豊富な知識を相手に押し付けている場合があります。
「森田先生はこう仰っていた」とか「全集五巻にこのように書かれている」とかの話をするのですが、必ずしも相手の悩みに寄り添ってはいない。
今の私も実はこのタイプに属するのかも知れないなぁ、と自問自答する時があります。このタイプにならない為に気をつけているのは、まず相手の話をキチンと聴くことだと思います。そうしてすぐに結論を出さない。何かアドバイスめいた事を言いたくなっても、ぐっとこらえて自分の中に飲み込む。時期が来るまでは、森田の話はしない。そう心掛けているつもりです。
経験主義の人
このタイプの人は、昔はともかく今は本などあまり読まず、ひたすら自分の人生経験からのみアドバイスする人です。発見会でなくとも、お年寄りには一般的にこのタイプは多いと思います。「ひょっとしたら、自分の経験からのみでは余り言えないのかも知れないなぁ」などとは余り考えない。あくまで自分の経験から得た教訓などを相手に押し付けている。
私が初心者として集談会に出席し始めた頃に、ベテラン会員達から受けたアドバイスに対して、実はこのようなものを私は何となく感じていました。
「この人が言っている事は確かに正論かも知れないが、私の悩みに向き合ってくれてはいない」何となくそう感じていたのでした。
河合隼雄(有名な精神科医です)「100%正しい忠告はまず役立たない」という文章が発見誌に紹介されていました。
自分が体験したことが他者には同じ意味を持たない。誰しもが正しいと思う100%正しい忠告は一般論であり、患者の個別を無視しており無力である。
『Hakken』2024年7月号(p34)
それと、私が最近最も感銘を受けた言葉は、実は大分集談会ホームページの言葉なのです。
それは、集談会に出席した人間関係に悩む人に関する記述でした。
つい、「○○したら?」とアドバイスしたくなりますが、それは無意味なことだと思いました。発見会としては、解決策はなく、ただ聴いて共感するしかありませんでしたが、一気に答えを出さず長い目で見るのも一つの方法なのかと思いました。
森田正馬も言っています。
森田全集五巻P38 なお重ねていいたい事は、他人の症状の苦しみに対して、あまり気早く批判する事を遠慮しつつ、なるほどやっぱり苦しいかなぁ、とお互いにしばらく考え合うだけの時間と余裕と思いやりとがあって欲しいものである。
アドバイスの問題 その2
発見会のベテラン会員がなぜアドバイスする事が好きなのか。理由は二つあると思っています。
① アドバイスすると気持ちいいから。他人にアドバイスすることで優越感を感じるから。そういう自分に酔っている。自己陶酔。
② 何か言いたくなった時にグッとこらえて言葉を飲み込むことが出来ない。我慢出来ずについ何か言ってしまう。言ってスッキリしたい。
どちらも意識するしないに係わらず、誰しもが少しはその要素があると思います。
①については「優越感を感じるから」などと書くと語弊がありますが、ようするに「自分の存在意義を感じる」という事だと思います。特にベテラン会員が症状が治っても集談会に出席し続けている理由として、①があることは否定できないと思いますし、その事を全否定してしまうと多くのベテラン会員達が発見会を辞めてしまうかも知れないとさえ思っています。
問題なのは、その事を全く自覚していない場合なのだ、と私は思います。
しかし②については、「スッキリしたい気持ち」「自分の衝動を我慢出来ない」という「かつて症状を形成した心理」がまだ残っている可能性だってあります。その事を時々は自己内省してみる必要もあるのではないか、と私は時々思うことがあります。
さて、ここまで随分とエラそうなことばかり書いてきました。
では、私自身はどうなのか。
今現在の私は、少なくとも①は全くないと断言できます。②も最近はあまりない。
しかし、以前の私は全くそうではなかったのでした。
以前の私は②の最たるものだったのかも知れません。そこにイライラ感や怒りも混ざっていたかも知れません。「この人は森田を学習している癖に、まだその事が判らないのか」とか「愚痴ばかり言って、実践しようとしないじゃないか」とかで、イライラして、つい必要以上の事を言って相手を傷つけていたかも知れません。それは一種悪意のこもったアドバイスだったかも知れない、それにほとんど相手の人格否定をしていたかも知れません。今は反省しています。
ベテラン会員になればなる程、人にアドバイスする事はあっても、自分が人からアドバイスを受ける事など、まず無くなってしまいます。そうなると、アドバイスされる側の気持ちが判らなくなってしまうものです。相手は有難く思っているはずだ、と思い込んでしまうのです。
私がそのことに気づいたのは、ある出来事がキッカケでした。
ある時、私は職場の人間関係の愚痴を家族にこぼしたのです。その時、家族は頼みもしないのに「こうすればいいじゃないか」とか色々と私にアドバイスするのです。私にとってそれは有難迷惑やオセッカイ以外の何物でもなかったのでした。「そんなことくらい言われなくても判っている」と私は思いました。私はただ黙って私の話を聴いて欲しかっただけなのでした。
その時私は気づいたのです。「そうか、自分は集談会で同じような事をやっていたのか」と気づいたのでした。
それ以降、私は、相手から求められない限りは何かアドバイスしたい気持ちを出来得る限りグッと飲み込むように心がけました。
ところが、私がせっかく我慢しても、他のベテラン会員が、私が言いたかったけど我慢していた事を、ズケズケとアドバイスするのです。
「ああ、この人が台無しにしている」と思いました。
言われた本人は、次回から集談会に出席しなくなりました。しかし言った本人(ベテラン会員)はどこ吹く風です。
ある時、支部からの派遣講師が集談会に出席しました。その時の感想を講師の方は私にこっそりこう言いました。
「この集談会は、アドバイスする人とアドバイスされる人とが、ハッキリ分かれているね」と。
そんな事から、私は次第次第に集談会に行くのが嫌になって来たのです。
集談会での違和感
私は、集談会に出席する事が嫌で嫌で仕方がなかった時期が一時ありました。そうなった経緯については後述したいと思いますが、ベテラン会員が何だかエラそうにアドバイスする姿に違和感を覚えるようになったのです。私自身がベテラン会員としてアドバイスする立場なのに係わらず、ひとたびそのように感じてしまうと、その嫌悪感に支配されてしまう性分なのです。
ちなみに「アドバイス好き」と入力してネット検索してみると、否定的な意見が沢山出て来ます。アドバイスするのが好きな人はオセッカイで自分の意見を人に押しつけているとか、それによって優越感を覚えている、とかです。
私が一般会員なら、嫌になったなら集談会への出席をやめれば良いだけなのですが、その時私は代表幹事であり、責任上も辞めるにやめられなかったのでした。
下の挿絵は発見誌の表紙にもなっているタナカサダユキさんが描いたものです。毎年の発見誌新年号での「発見会川柳」での挿絵です。
私は、これを見た時に抱腹絶倒で、大笑いしてしまいました。この川柳を書いた人は素晴らしい人だと思います。自分(自分達)の事を非常に客観的に観ているからです。物事を客観視できる人は本物です。このような人はきっと症状が再発することもないのかも知れません。それにユーモア精神も、やはり自分(自分達)を客観視しているからこそ、生まれるものなのです。
逆に、客観視できない人は「自分は森田学習のお陰で普通の人以上になれている」とか、自分は森田で言うところの「陶冶期に入っている」とかを大真面目で言える人だと思います。
その頃の私は、ベテラン会員がホワイトボードの前に立って滔々と森田理論について講義する姿にも、違和感を感じるようにもなっていました。
自分を「森田の先生」だと思っていらっしゃる。専門家以上に森田に詳しいと思っているのかも知れません。
「無知の知」という言葉があります。
「自分は何も知らない」ということを知る事こそ、最高の知性であり教養である、という意味の言葉です。
森田正馬は患者達に以下のような話をしています。
(全集五巻P590) ある学者は、70歳を過ぎてから「自分の研究は何も得るものがなかった」と言った。しかし他人からみれば非常にエライ人である。研究が進めば進むほど次から次へと疑問点が出て来て果てしがなくなる。このような人がよくわかった偉い人である。
また、以下のようにも言っています。
自分は偉いと思う人は、偉くない人である。(全集五巻P245)
(全集五巻P470) (学者、道徳家、宗教家などは)この様な人は、自分自身が道徳を実行するのが目的でなく、他人に道徳をさせるのが目的である事が多い。(中略)理屈ほど都合のよいものはない。人が道徳の教えなどあまりよく知り過ぎると、人の欠点ばかりとがめて、自己内省はお留守になる事がある。
生活の発見会は「相互学習の場」をうたい文句にしているはずです。会員相互が対等平等な立場で学習するのがタテマエのはずです。しかし、ベテランになると「先生」になりたがる人が多い。先生と生徒という関係性が出来てしまっていないか? あるいは医師と患者? 牧師と信者? それが、当時私が抱き続けて来た疑問でした。
ベテラン会員の中には、以前の反動で、自己内省をやめてしまった人がいるのではなかろうか、と私は思ったものです。他人に対しては自己内省するように教え諭していながら、自分自身の内省はおろそかになっていやしないか。
そんなこんなで、私は集談会への出席が嫌になっていたのでした。
私がそんなベテラン会員に対して言いたかった事を、森田正馬が以下の言葉で代弁してくれています。
(全集五巻P574) この会での修養で、自我執着が治ると、今度は前の反動で、自分も人と同様という平等感にとらわれて、自分の心をもって、直ちにこれを人に押しつけようとする。いずれもまたいけない。人の心は千変万下であるという事に思いを潜めなければならない。
(全集五巻P77) 人に対して親切の押し売りをして、強いて自分の意見をもって人に押し付ける事は、誠によくない事かと思います。
(全集五巻P734)(要約) 「己の欲するところ、これを人に施せ」・・・随分積極的だが、人の迷惑になるような事をも人に施して、相手が困る事がある。神経質は消極的だから、こういうやり方は向かない。「己の欲せざるところ、これを人に施すなかれ」の方が良い。
さて、私が集談会に対し違和感を感じ始めたキッカケは明確には思い出せないのですが、漠然とした記憶としていくつかの思い出せるエピソードがあります。
ある時の集談会に「10年前に一度集談会に出席した経験がある」という人が来ました。
「10年前にはなぜもう一度出席しようと思わなかったのですか?」と私は質問しました。
彼はこう答えました。
「何だか森田教の信者の集まりみたいに感じたから」だと言います。
私は「今度はそう思われないようにしよう」と思いました。
ところが気づくと私は
「森田のお陰で自分はこんなに行動できるようになった」という話ばかりしていました。
明らかに自分に酔っていたと思うのです。それは自分の自慢話への心酔です。
その時の集談会に居合わせた他のベテラン会員達も、皆口々に同じように、「森田のお陰で自分はこんなにも立派になれた」という類の、一種の自慢話のオンパレードです。
ふと彼を見ると、苦笑いの表情を浮かべていました。
私は彼の表情を察し「シマッタ」と思いました。(・・・彼はその後、二度と集談会には顔を出しませんでした)。
私はその日の夜は、一睡も出来ませんでした。
眠れなかった理由を私は
「昼間に興奮して喋り過ぎたから、その興奮が夜になっても覚めていないようだ」と自分でそう思いました。自慢話に心酔し過ぎて興奮してしまったと思ったのです。
ずっと後になって、その夜に眠れなかった本当の理由が判りました。
それは自慢話をして興奮してしまった自分への嫌悪感と後悔なのです。
私の心の奥底に、そういう軽はずみな自分を責める気持ち(自己内省心)が潜んでおり、そのせいで眠れなかったのです。(自己内省心というのは決して悪いものではなく、むしろ人間的成長には欠かせないものです。)
森田正馬の時代にも、形外会の会員達の意識はだいたい同じようなものだったようです。会員達が口々に「神経質は普通の人より素晴らしい」と自画自賛するのを、森田先生は以下のように言って戒めています。
森田全集五巻P340 「普通の人」と神経質と比較すると言っても、「普通の人」という事の意味が、限定されていないから、比較のできない事である。 (中略)僕が神経質を礼賛するのは、真珠が好きだというくらいの事です。いやルビーだオパールだと争うのではない。(中略)他と比較しての事ではない。
森田全集五巻P148 森田を信じるのも、迷信教を信じるのと同じである。我々は常に疑い、絶えず自由に体験し、決して盲信してはならない。(中略)自分も自分の治療法を絶えず疑いつつ進歩しているのである。
森田全集五巻P203 (私の説明は)ちょっと変形すると容易に宗教的な気分になりやすい傾向がある。それ故に私は患者に対して常にそうならないように、科学的に物を正しく見るようにする事を忘れないようにさせている。
もうひとつ想い出せるエピソードがあります。
その人はかつては毎月必ず集談会に出席していた常連でしたが、今はもう症状の悩みもなく、ここ20年近く集談会に出席することはなくなっていました。
でも年に一度だけ、飲み会には出席する人です。
その彼がある時、酒を飲みつつこう語りました。
「自分の妻が集談会に出席した時の第一印象を、こう言っていた」
(その人が最初に集談会に出席した時は奥さん同伴だったのです。)
① 「森田、森田って言うけど、当たり前の事を言っているだけじゃないか」
② 「ベテラン会員に対して【変わった人】だという印象を受けた。むしろ悩んでいる初回者の人の方がずっと普通の人だと思った」
私は、その時には彼の話を「へーぇ、そんなものかな」と聞き流していました。
しかし、後になってその意味を理解しました(たぶん)。
「森田は普通のことを言っているだけ」とは、発見会会員からも昔から時々言われていました。確かにそうだと思います。世の中で大きな成功を収めた人などの伝記などを読むと、森田を知らない人なのに、森田と同じようなことを言っているという事はよくあります。当たり前のことを当たり前にやれば、それはすなわち森田なのだと思うのです。神経質人間はそれが出来ないから、森田先生が「人間の再教育」をしていただけなのでしょう。
そのように当たり前のことを、森田学習をしたベテラン会員が、さも「自分だけが知っている特別な理論」であるかのようにエラそうに講釈している姿をみて、彼の奥さんは「変わった人だなぁ」と感じたのかも知れません。
私はそういう幾つかの体験を重ねつつ、いつの間にか集談会に対し冷めた目で見るようになっていき、違和感を感じるようになったのだと思うのです。
昔観た映画がありました・・・・敬虔なクリスチャンだった人が、ある時、牧師や宗教の偽善性に気づき、信仰を捨てて自由奔放に生きる決心をする・・・・という内容でした。当時の私は、それと似たような心境だったのかも知れません。
私が反省すべき点
私が発見会から離れなかったのは、他集談会の人達との交流が楽しかったからです。
他集談会の人達は概ね和気あいあいとしていて、アドバイスや理論学習だけでなく、集談会終了後に飲み会を開いたりして、遊びの要素も取り入れていました。遊びの要素が少しはなければ、症状の悩みから解放されたベテラン会員が集談会から離れて行くのは当然だと思うのです。
しかし、所属集談会への批判的な目は変わりませんでした。
そんなある時のこと。私は小説を読んでいて、以下の文章に、ある種の感銘を受けました。
「木戸はつねに池のふちにいる。大久保はつねに飛び込んで池の中にいる」
と、この当時評した者がある。鯉をつかまえねばならぬときに大久保はみずから体を濡らして池の鯉を追ったが、木戸は濡れるのを厭い、池のふちから指図をしたり批判したりした、ということらしい。
木戸は大久保が苦手であった。大久保の無私と、諸価値を計算しぬく慎重さと、そしてその強烈な実行力を評価する点では、木戸は決して、例えば大久保好きの伊藤博文などに劣らなかったが、しかし肩をならべて仕事をする気にはなれなかった。 『翔ぶが如く』司馬遼太郎 文春文庫
木戸孝允・・・幕末期は桂小五郎という名前だった。坂本竜馬と伴に明治維新の実現に向けて活躍したが、維新後は不平不満ばかりでうつ病的になり、何も成し得ないまま病死した。
大久保利道・・・明治維新後に最も活躍した政治家。恐らくこの人がいなければ明治時代はあり得なかったとも思える程の数々の活躍を成すが、強引で冷酷な面もあって人々から恨まれ、のちに暗殺された。
おやおや、ここに書かれている晩年の木戸孝允はまるで自分のようではないか、と思ったのです。評論家のように批判ばかりして、具体的な行動には出ようとしていないではないか。
しかしこの場合での具体的な行動とは、ベテラン会員の意識を変えさせることだとも思えますが、人の心を変えさせるのはそもそも無理なのです。それに私の考えが正しいとは限らない。
ならば、不平不満を抱いたり、評論家になるのはもうやめよう。そう思ったのでした。
以下は同じ小説にあった表現です
「肥後人の理屈好き」というのは天下に知られた通弊で、肥後人が十人集まれば十人とも意見が違うといわれ、それぞれが他人の意見との小さな差を重大なものとし、その小差に固執する。そのために大事をなすときに決断が遅れ、行動が時機を失し、とくに集団として行動することが困難であった。
これはまさしく神経質人間の特徴か!と思いました。
(肥後とは熊本県のことですが、当時はともかく、少なくとも発見会で知り合った熊本の人にはそのような人は一人もいませんので、誤解なきようお願いします。)
このように、読書によって気づかされることは多くあります。
本来ならば、このような事を悟るのに、読書よりも実体験から悟るべきなのかも知れません。しかし、若い時ならともかく、65歳を超えた男性に対し「あなたは批判ばかりしていて、実行しないじゃないですか」などと注意する人がいったいどこにいるのでしょうか。年配者に対して意見する人などいないのは、むしろ常識です。ならば年取った人はどこで学べば良いのでしょうか。私は読書しかないのかな、と思っています。その意味でも読書をしない高齢者は、問題点があっても改善の余地がないのだと思えるのです。
読書という趣味があって良かった!! とつくづく思います。
以下の森田の言葉は、神経質同志の結婚が向かない理由として森田正馬が述べたことですが、このことは結婚のみでなく、神経質同志の人間関係にも当てはまることだと思います。
P729 神経質同士は、お互いにこの心持がわかり、心の底まで見透かしているから、互いにその欠点を挙げあって、相手ばかりにそれを改善させようとする。
私はこの森田の言葉を知った時、「だからアドバイス好きのベテラン会員は、人の欠点ばかり指摘して相手ばかりに改善させようとせずに、自分自身のことも振り返って改善すべきではないか」と思ったものでした。
ところが、最近ハッと気づいたのですが、それは私自身のことにも言える事でした。私もまた、相手(アドバイス好きのベテラン会員)の欠点ばかり指摘して、相手ばかりを改善させようとしていたのでした。