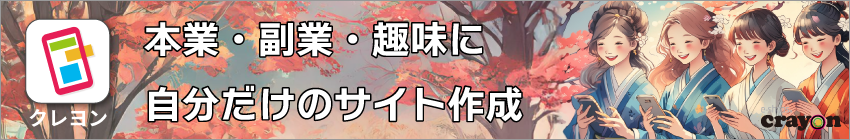読書について
森田正馬は大変な読書家でした。様々なジャンルの本を読んでいたようです。その事は『森田療法の誕生』畑野文夫著 三恵社 に詳しく書かれています。
また、森田正馬全集第五巻にも、森田先生の以下の発言が記載されています。
本はいくら読んでも読み足らぬ。なるべく多く本を読みたいから、不眠に苦しむことはない。むしろ不眠があるほど良い。森田全集五巻P333
夜中でも目が覚めたら本を読む。本が面白いと、時には片方ずつ休めて、交代に目をつぶって読むような事もある。森田全集五巻P380
私は18歳の時からいままで42年間、日記を一日も欠かした事はない。近年の読書が、雑誌や調べものは別として、一年に平均60冊余り・・・ 森田全集五巻P432
世間一般では「読書が好きです」と言うと、「この人は社交性に欠けた変人かも知れない」と思われる傾向もなきにしもあらずですね。私自身の若い頃を思うと、確かにそれも否定はできません。
ですがそれは、「読書好きの中にはそのような人もいる」ということにしか過ぎません。
例えばホリエモンの愛称で知られる堀江貴文も読書好きで有名な人ですが、彼ほど社交性と行動力のある人物も少ないでしょう。
アウトドア派の作家として知られる椎名誠は、自分のことを「活字中毒者」と言っているほどの本好きです。旅行では何冊もの本を持参し、旅先でも必ず地元の書店に寄るとのこと。書店のない辺境の地などで読む本が無くなると「どうしよう」とパニックになるそうです。
伊藤忠商事(株)元社長で『死ぬほど読書』著者の二羽宇一郎は、読書と仕事と人付き合い、その三つのバランスが取れてこそはじめて良い仕事が出来ると書いています。読書好きの人が時に偏ってみえるのは、そのバランスが取れていない場合なのでしょう。(私がまさにそれでした)。
社会人として一生平社員で良いのなら読書など必要ないのかも知れません。しかし大きな組織の上層部の職責にある人で「読書などしない」という人など、まずいないのではないでしょうか。
お笑い芸人でありながら小説を書き芥川賞を受賞した又吉氏の書籍に「なぜ本を読むのか」、その理由が明快に書かれていますのでご紹介します。
「なぜ本を読むのか」
〇普段から何となく感じているものの、その曖昧な感覚や感情を頭の中でどうにも整理できない時、本を読んでいて「まさにこれだっ!」と自分が何となく感じていたことを再確認できる。それによって自分の複雑で曖昧だった感情を、言葉で明確に整理できるようになる。
〇それまで自分になかった新しい視点や価値観をもたらせてくれる。(その際に必要なのは、自分の価値観と異なる内容を頭から「共感できない」と否定しないことだと言います。)
自分がわからないものを否定し遠ざけ、理解できること、好きなことだけに囲まれることは危険です。
すべてに共感するのではなく、わからないことを拒絶するのではなく、わからないものを一旦受け入れて自分なりに考えてみる。
『夜を乗り越える』又吉直樹 小学館よしもと新書
又吉氏はそれによって「思考の幅が広がる」と言います。
〇読書の利点として「何度でも読み返せる」「再読してみると、以前とは全く違った視点を再発見できる」とも書いています。
これらの事はまさに、森田学習をする時の姿勢としても当てはまるような事だと私は思いました。
さて、私自身は子供の頃から読書が好きな訳ではなかったのです。高校を卒業するまではコミック漫画しか読んだことはありませんでした。
そんな私が大学一年生の時、教授から「夏休み期間中にこの本を読むように」と指示されたのです。今思うとその本は本当に薄っぺらな文庫本でした。しかし当時の私はその文庫本一冊を読破するのに、まさに七転八倒の思いでした。40日余りの期間をかけてやっとの思いで読み終えた時には本当にホッとしたものです。
読書嫌いだった私が大学を目指すなんて、進学の動機がそもそも間違っていたとは思いますが、私は逆に大学に入ってから読書という習慣を身に着け、それが一生の財産になったのでした。(SU記)
◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇
以下の内容は森田初心者向きの内容ではないかも知れません。
どちらかと言えば、ベテラン会員向けに書いたものです。
森田の核心
森田の核心は何か?多くの人が、それは「あるがまま」だと言うのではないでしょうか。確かにそうだとは思います。しかし「あるがまま」は「あるがままになろうと意識すれば、それは最早あるがままではない」と言われるように禅問答のようで抽象的です。もっと具体的なもので「これぞ森田の核心だ」と言えるものはないのか。・・・それは人それぞれ違うのかも知れません。私自身が現在考えている「森田の核心部分」とは以下のようなものだと思っています。
森田正馬の以下の言葉に出会ったのは2018年頃だったと記憶しています。
その時には「ああ、そうか」という程度の感想だったと思います。
発見会でも、多くの人達がそんな程度の感想しか持たないようです。
「性格の違う人とは交際ができない」(どうすれば良いか)とかいうような質問は、典型的な神経質の特徴であって、神経質でない人は、ほとんどこのような質問はしない。
普通の人は、誰でも、嫌いな人は不快であり、性格の異なる人とはソリが合わない。当然の事である。これを抑圧しようとも、どうしようともせずに、ただ我慢して境遇を押し切り、運命を切り開いて行こうとしている。
これに反して、神経質は自己中心的な功利主義から、自分の苦痛を最も少なくして、最も大なる幸福を得ようとする工夫から、楽々と愉快に人と交際し、何事にも自分の思い通りにしたいと考えるからであります。(『森田正馬全集第五巻』P571)
※神経質・・・・森田正馬は症状に悩む神経質性格を持った人の事を、単に「神経質」と呼んでいました。一般的に使われる神経質という言葉とは意味合いが異なるので注意が必要。森田先生は「普通の人」と対比する意味で「神経質(の人)」という言葉を使っている。
※功利主義・・・快楽を求めて苦痛を避ける傾向。苦痛を悪だとみなす。
最初はこの言葉の最初の部分「神経質でない人はほとんどこのような質問はしない」という部分のみに着目して「なるほど、そんなものか」という程度の感想でした。
それから5年ほど経った時の事だったと思うのですが、
私は再びこの文章を再読した際、
今度は「そうか!そうだったのか!」と愕然としたのです。
5年前には気づけなかったことに、その時気づいたのです。
それは、この森田の言葉の最後の部分です。
自分の苦痛を最も少なくして、最も大なる幸福を得ようと工夫する
何事にも自分の思い通りにしたいと考える
という部分です。
私は、これぞ「森田の核心」ではないか、と思ったのです。
森田正馬は「神経質性格の物の考え方」を骨の髄まで見抜いていたのだなぁ、と私は感銘を受けました。
神経質性格の人は
「何事も自分の思い通りにしたい」
という傾向が普通の人より強いのです。
しかも
「嫌な思いをせずに(苦痛なしに)思い通りにしたい」
という考えも同時に強いのです。
ではなぜ、「楽して自分の思い通りにしたい」という考え方から「性格の違う人とは交際が出来ない。どうすれば良いか」とかいうような質問が生まれるのでしょうか。それは『魔法の杖』のように「楽して自分の思い通りに出来るような方法」を教えて欲しい、という気持ちからの質問なのです。きっと森田先生ならそのような極意を教えてくれるのではないかと期待しての質問なのです。
(また、そのような考え方から森田学習をするのであれば、森田学習をする動機そのものが根本的に間違っていることにもなります。)
神経質の人は楽々と物事を解決できるノウハウを捜し求めている。普通の人は「そんな簡単な王道などない」と嫌な事にも普通に我慢しており、我慢して耐えながらも、少しずつでも物事を前に進めるようにと地道な努力もしている。しかし神経質の人はじっと耐えて我慢することや地道な努力が嫌なのです。
このような考え方が症状を生む原因のひとつにもなっている事に気づく必要があります。
まず、世の中のことを自分の思い通りにしたいという意識がとりわけ強い。・・・そう書くとまるで、わがままで傲慢で自己主張の強い人を想像してしまいますが、神経質人間はそう単純ではありません。一見すると大人しく控えめに見える人でも、実はそのような意識を秘めているのです。体調はいつも万全でいたい。病気には絶対になりたくない。夏暑く感じないようになりたい、冬寒く感じないようになりたい。そんなふうに何にしろ自分の思い通りになりたいのです。
人間関係でも、自分が主役でいたい。脇役にはなりたくない。いつも自分が優位に立ちたい。優越感を感じていたい。(症状が治った以後にそのような負けん気が表面化する人が多いような気がします。いわゆる「ベテラン」にも時々そういう人がいます。)あるいは、体調はいつも万全でいたい、等々。そんな意識がとりわけ強い人が、神経質人間のなかには多いような気がします。
そして、それが叶わなくなるとストレスを感じてしまい、それが原因となって症状を発症するのです。
そうして症状に囚われるようになると、今度は症状を無くす為に、自分の感情や性格を思い通りにコントロールしようとします。自分の心や気持ちを自分の思い通りに変えようとするのです。
佐賀集談会のMさん(職業は医師)は、神経症とは「スッキリしたい病」だ、と言っておられました。自分の理想通り(思い通り)のスッキリした気持ちでいたいのです。そうでなければ我慢できないのです。
対人関係でうまくいかないと心の中がモヤモヤします。このモヤモヤ感を一刻も早く取り除きたいと思う。いつもスッキリした心でいたいと思う。「なんだかスッキリしないなぁ」という違和感を取り除こうと努力すればするほど、ますますその違和感が強くなっていきます。それが症状となって固着するのです。
ガスの元栓や鍵を閉め忘れていないか、手洗いを繰り返す等、何度も何度も確認行為を繰り返す人の心もまた同じカラクリです。このモヤモヤ感を一刻も早く取り除きたいと思う。確認してスッキリしたい」。自分の思い通りにスッキリしたいという気持ちがとりわけ強いのです。
病気を恐れて病院廻りを繰り返す人の心理も同じです。安心したい。このモヤモヤ感を一刻も早く取り除きたいと思う。自分の思い通りにスッキリ感が得られるまで納得しない。
いつも身体の様々な部位の体調不良に悩む人の心理も同じです。いつもスッキリした体調でいたいと思う。このモヤモヤ感を一刻も早く取り除きたいと思う。自分の思い通りにスッキリしたいのです。
中には「病気が怖くならないようになりたい」とか「死ぬのが怖くないようになりたい」という人もいます。そんな人などいません。自分の心を自分の思い通りに操作できると勘違いしているのです。
不眠に悩む人も、眠れないことそれ自体よりも、それ以上に、眠れないことによるモヤモヤ感が嫌なのです。スッキリしたいのです。自分の思い通りの睡眠を得たいのです。
吃音に悩む人も、どもることそのものより、それ以上に、吃音によって劣等感を感じてしまうそのモヤモヤ感が嫌なのです。いつも優越感を感じていられるような「思い通りの人生」を求めているのです。
神経質性格の人は
「何事も自分の思い通りにしたい」
しかも「嫌な思いをせずに(苦痛なしに)思い通りにしたい」
このような観点で森田関連書籍や発見誌を読むと、森田正馬と同じようなことを、他の人達も言っている事に気づきます
名文発掘 「心を強くする生きかた 自己中心からの解放」 長谷川洋三
(『HAKKEN』(生活の発見誌)2023年12月号記事より)
「取り越し苦労ばかりして、積極的行動に出られない」と悩む人は・・・
この悩みの根本は、取り越し苦労なしに積極的な行動に出たい、というところにあるのではないか。嫌な思いや心配をしないで、積極的行動に出たいのだがそれができない、というところにあるのではないか。
楽々と努力したいというのと同じである。無理な注文というものだ。
(中略)私たちの学習の第一の標的は、この「悪知」の打破でなければならない。
森田療法は我々に何を教えてくれるのか ~症状レベルから生きかたレベルへ~
潤クリニック院長 樋之口潤一郎(じゅんいちろう)
(HAKKEN2023年7月号記事より)
神経質の人は、コンビニエンドな(便利な、手ごろな)ものにとらわれるんですね。
違うんです。(中略)逆に大いに悩んで欲しい(中略)悩まないで通り抜けようとするから、自縄自縛(じじょうじばく)に入るわけです。
しっかり悩んで、現実を見つめていく。すぐに不安をなくそうとする態度から、不安はなくならないけれど、試行錯誤して、現実の生活をどうにかしていこうという、態度の転換を図るということなのです。
そのようにして、症状を克服したとして、症状は克服したけれども、今度は・・・・・
そうすると、全部万能にしたい、思うように進めたいという、気持ちの強さも出てくるんです。この思い通りにしたいという気持ち、これが神経質性格のいわゆる陶冶、成長の過程で、絶対打破していかなければいけないものです。世の中、全部思うようにいくのかといったら、そんなことないんですね、絶対。
部分的引用では先生が何を言いたいのか、わかりにくいかも知れません。
発見誌に書かれていた内容全体の要約をすると、こういう事のようです。
神経質の人は「こうすれば悩まずに、すぐに問題を解決できる!!」 というような「コンビニエントなもの」を求める傾向がある。「悩まないで、楽々と通り抜けたい」
それは違う!! と樋口先生は仰っている訳です。
おおいに悩む事で、人間的な深みが出て、やがて症状も軽減しますよ、と先生は仰っているのです。
・・・そうして症状が軽減すると、自分は何でも出来るという自信がついて来る。
そこで、何でも思い通りにしたいという、神経質の別の悪い傾向が前面に出て来る。
しかし、人生はそんなに簡単なものではない。何でも自分の思い通りに出来るほど人生は甘くはない。・・・最終的には、そこを打破しないと、神経質人間の本当の良さを発揮する為の最終段階は通過出来ない。
★お断りせねばならないのは、「何事も自分の思い通りにしたい」という意識は症状を生む一因ではあるものの、それだけが症状の原因ではないのは当然です。世の中には神経質人間以外でも自分の思い通りにしないと気が済まないというタイプの人は勿論沢山います。その人達全員が神経症になる訳ではなく、そうならないのは、元々の生まれ持った神経質の素養がないからです。森田正馬のいう「ヒコポンドリー基調」があるかないかの違いです。しかし逆に、生まれ持った神経質の素養がある人でも、「努力せずに楽に自分の思い通りにしたい」などという虫の良い考え方をしない人は、神経症にはならないのも事実だと思います。そのような人は、何でも自分の思い通りにしたいとは思っていないし、時として我慢して耐えることも当然だと思い、地道な努力をいとわないタイプの人なのです。
森田正馬は神経質性格の人を以下のようにも言っています。
いやな事を、いやでなくしておいて、それから手を出そうとするのが、神経質の通弊でありズルイところである。 (全集五巻P409)
どうも神経質の人は、判断が窮屈でいけない。物の見方が一面的・独断的である。
つまり早く一定の判断をして解決し片付けようとするからでもあろうか。
(全集五巻P574)
また我々の仕事なり、能率なり、すべての行為について、神経質は、これを最も自分の都合のよいように、公式にあてはめ、一定の標準を立てようとする。まことに便利であるようであるけれど、世の中の事は決してそんな単純なものではない。 (全集五巻P574)
「疲労した時は、休息すべきか、もっと働いてもよいか」などいう問答も、みな同様の理想主義の型にはまったものである。(中略) 決してあらかじめ公式をもって定めておくことはできない。(中略) 決して一律にいう事はできない。 (全集五巻P575)
時と場合における事情は、常に複雑極まりのないものであるから臨機応変で、決してこれを「どうすればよい」とか鋳型にはめるべきものではないのである。
(全集五巻P568)
森田正馬の言っている「神経質人間の考え方の特徴」をかいつまんで言えば、つまりこういう事になると思います。
○その場その場で考えるのは面倒なので「こんな時は、こうすれば良い」とあらかじめ一律に決めておき、その公式通りに物事を処理したい。その方が楽だ、と考える。臨機応変が苦手で、型にはまった考え方を好む。
○ 手っ取り早く問題を解決してしまいたい。公式通りに決めて、早く結論を出してしまいたい。
確かに、そのような考え方は一見すると理にかなっているようにも思えます。ビジネスの問題解決法としては、それもある程度までは正しいのかも知れません。
しかし、その考え方をそのまま「心の問題」や「生き方の問題」「人生の問題」などに当てはめようとすると、それは間違いを生む事になります。「人間関係の問題」にしてもそうです。
森田正馬の言う「世の中の事は決してそんな単純なものではない」ということです。
しかも、神経質の人は考え方が非常に硬直的なのです。ビジネスにしても状況は刻一刻と変化するものですが、神経質の人は「この方法が正しい」と一度方針を決めたら最後、臨機応変に変更することが出来ないという傾向があります。
そのように考えると、集談会での理論学習も、以下のような問題をはらんでいると私には思えるのです。
発見会の『森田理論学習の要点』も、そのような感覚から学習してしまうと、「型にはまった公式」を学ぶ為のテキストになってしまいかねない。神経質の人は「こうすれば、こうなる(良くなる)」という公式的なものを求めており、理論学習はその傾向を助長することにもなりかねない、とも思えるのです。
もう一度、森田正馬の別の言葉を紹介します。
普通の人は、自分は頭が鈍いということを承知して、ますます勉強しようとするが、神経質は、その鈍いことを薬や奇術によって頭を良くしようと迷いを起こし(以下略)
(全集四巻P487)
神経質の人は、手っ取り早い解決法である「薬や奇術」「魔法の杖」を求めるのと同じ気持ちで、発見会で森田学習に励んでいる。そんな可能性も否定できない。時として私はそう感じることがあります。
症状の苦しみをひきずりながら進むということが、いまの自分にとって「あるがまま」だということに気づいていない。あるいは、「あるがまま」を理解したと言いながら「苦しまないで前進することだ」と思い込んでいるからではなかろうか。
症状は一種のクセである。心身に根づいたクセである。新しいクセを養成するまでは、古いクセの抵抗を覚悟しなければならない。症状の苦しみをひきずりながら進むほかないのである。
『Hakken』2023年12月号 名文発掘 「心を強くする生きかた 自己中心からの解放」長谷川洋三
「無くて七癖」と言われるように、自分のクセを本人自身が自覚する事はなかなか容易ではありません。しかもクセというものは長年にわたって身体や頭脳に沁み込んだものなので、すぐに改善するのは無理なのです。「ああ、また悪いクセが出たなぁ」と自覚するだけで良いのです。
森田正馬は
「やりくりや工夫はいらない。ただ自覚さえすれば、それで良い」
と言っています。
悪いクセを治そうと努力したり、やりくり工夫する事が、すなわち精神交互作用となって逆にクセを悪化させる原因となります。クセを自覚するだけ。ただそれだけで良いのです。あとは、世の中、なるようにしかならない。
発見会本部HPに以下の森田正馬の言葉が紹介されています。
普通の人は、自分の人生の目的のために、なるたけ細かく苦労することを当然のことと承知の上でやります。なのに神経質は自己中心的に、知恵の周りが良すぎるために、自分勝手な都合のよいことを考え出すのであります。すなわち自分の人生を完全にしようという大望を持ちながら、しかもそれを安楽に取り越し苦労なしにうまくやろうという、ずるい考えを起こします。たとえば苦労せずに金持ちになろうとするのと同様です。強迫観念にかかっているものは、自己一点張りのために、決してこのことに気がつかないのです。
私は、発見会の『森田理論学習の要点』のような教材を使用した標準的な学習では、そのような自分のズルイ考え方の特徴を自覚する事は出来ませんでした。森田正馬の言葉をじかに読んでから、ようやくそれに気づいたのでした。
その意味でも「全集五巻」で直接森田の言葉に触れることは森田の真髄を学ぶための最高最大の教材だと私は思っています。
「発見誌」2024年3月号の関東第一支部の報告(P34~)に「全集五巻」について「森田療法を学ぶ会の会員になった以上、みなさんには【本物】に触れて欲しい」との意見が書かれていますが、私も全く同感です。
そのうえで「森田理論は症状をなくすことが第一ではなく、人生観を変えることが第一であるということを認めるか否かで森田理論の学び方が変わってくる」としています。この解説は私にとっても「目からウロコ」でした。
また「(症状)軽快後の人たちには独特の課題・傾向がある」として、「『自覚』の不十分さ」等を指摘しています。それらのものを補うものとして、「全集五巻」による学びの有効性を説いているのです。
しかしながら「全集五巻」は難解で取り付き難く、また当時の時代背景等を加味して読まなければ誤解を生じてしまう部分も多々あります。
幸いに、九州にはMさん(佐賀県の医師)主催の「あるがまま研究会」(福岡市内で不定期開催。)があります。この会では「全集五巻」の森田正馬の言葉を主な教材として使用している模様です。
補足
神経質人間は、何事も自分の思い通りにしたいと考える、という事をしつこいほど書いてきました。我慢したり耐える事が苦手で、せっかちで早く問題を解決したいと焦る事も共通していると思います。この事は自分自身のことや過去に発見会で出会った多くの人たち(ベテラン会員を含む)を見ていて感じたことです。
しかし、地道な努力を嫌うという点においては、そうでない人もいます。中には、自分の願望を達成するために、偏執的なほどに努力を惜しまない人もいます。特に男性にこの傾向が顕著なような気がします。私が40年前に発見会に入会した頃の神経質の男性には、そんなタイプの人も多かったような記憶があります。時代的なものもあったのかも知れません。
「100%完全なものはあり得ない、60%主義で行こう」などと言いつつも、このタイプの人の60%は、いい加減な私から見ると150%だったりします。
それと、私が感じていたのが、このタイプの人の中には、保守的傾向が強くていわゆるリベラルな考え方に対して生理的に強い嫌悪感を持っているのかも知れない、と思えるような傾向でした。かと言って、無私の精神や滅私奉公の気持ちがある訳でもなく、むしろどちらかと言えば個人主義的な生き方をしていたりもします。そこのところのアンバランスさに私は不可解なものを感じていたのですが、以下の言葉を見て、私はその答えを見出しました。
以下は、作家の三島由紀夫を評論した文章にあった言葉です。
整序に対する偏愛、 執念と化した秩序愛
あっ、これか!! と私は思いました。物事が整然と秩序立って保たれていないと嫌なのです。執念と言えるほどに、その気持ちが強いのだと思います。物事が決められた通りに収まっていないと、生理的に受け入れ難いのだと思います。
それもまた、神経質人間の特徴のひとつか、と納得しました。
・・・・その後の私は、仕事を通じて「普通の人の生き方」から学ぶ機会が多くありました。つまり普通の人達はどんな感覚で生きているのか、それを知る機会に多く恵まれたのでした。普通の人達の生き方から学んだ事は、理論学習以上に大きかったように思うのです。
(普通の人は)どうしようともせずに、ただ我慢して境遇を押し切り、運命を切り開いて行こうとしている。(全集五巻P571)
(普通の人は)素直に我慢している(全集四巻P487)
まさしくそれです。
「症状を治す為」その手段として森田を学ぶうちは、決して森田の本質を理解する事など出来ないと私は自分の経験から、そう思います。また、「楽に生きる為」それを知る方法として森田を学ぶうちは、決して森田の本質を理解する事など出来ない、とも思います。
森田は「自覚を持つ為」に学ぶのです。森田正馬は、自分はいかなる人間か、自覚を持つことが大切だと言っています。そして「やりくり工夫はいらない。ただ自覚しさえすればそれで良い」とも言っています。「やりくり工夫」とは、こうすれば症状の悩みが少なくなるとか、 こうすれば楽になれるとか、です。あるいは自分はこんな人間だと自覚したのだから「ならばこの悪い性格を変えよう」とするのもやはり「やりくり工夫」です。森田正馬は、やりくり工夫はいらない、と言っているのです。「ただ自覚しさえすれば、それで良い」のです。「自分はこんな人間である」と自覚すれば、欠点は自然と是正されていくのです。確かにそれには時間はかかります。しかし、自分の欠点を変えようと何十年もモガキ続け、やりくりし続け、工夫し続けても、治らなかったことを思えば、自覚さえ持てばずっと短い期間で徐々にではあっても変わっていくのだと思います。大切な事は自覚なのです。
発見会の山中顧問は以下のように述べています。
(症状が再発する)根本理由は結局、ご本人の自覚、気づきが足りなかったからです。神経質のとらわれの根本的な解決は「ひとえに自覚にかかっている」と、森田博士がおっしゃっているとおりなんです。
『Hakken』(発見誌)2024年2月号 「森田で辿りつく静かで温かな世界」
森田先生は「森田理論」と呼ばれている事ばかりを患者達の前で話していた訳ではありません。例えば水谷氏(水谷啓二さん?)のイソップ物語の「ブドウとキツネの話」です。水谷氏は、若いくせに上司へのオベッカが上手い課長を、けしからんと思っていた。しかしそれは、ブドウを取ることが出来ないキツネが負け惜しみに「あのブドウは不味いに決まっている」と言ったのと自分は同じだと気づいた、という話。この話に森田先生はこうコメントしています。
今のような話は非常によい話です。こんな事がよくわかれば、神経症は治ります。
(中略)普通の人も、修養の心がけのない者は、この自分の心の状態に気がつかないのであるが、特に神経質は、自己中心的であるから、ひがみ・ひねくれの心が非常に強い。まず第一に、その心を打ち壊す手段が、すなわち治療法の眼目であります。(全集五巻P619)
森田正馬が一見すると症状とは別次元の、日常生活のなかでの「気づき」や「自覚」を重視していた事が判ります。
以上、随分と難解な事を書いてしまいました。
症状を治す為に森田を学習しているのに、「症状を治す為の手段として森田を学ぶうちは決して森田の本質を理解する事など出来ない」とは何を言っているのだ、と反論したくなるかも知れません。しかし「症状を治そうとすれば治らない」というのは森田の基本中の基本なのです。だのに「『症状を治そうとすれば治らない』という森田理論」を学習する事によって、症状が治る事を期待するとは、何という矛盾なのでしょうか。
そこに森田を「頭で理解する事の難点」があります。理論を頭で理解しただけでは症状は治らないのは、そのためです。
「自覚を持つ為」に森田を学習するのであれば、そのような矛盾はないのです。自覚を持つという事は、言いかえれば「自分を客観的に観る」という事にも繋がります。その時には、いつの間にか症状は治っているのです。
「『症状を治そうとすれば治らない』という森田理論」
それを学習する事によって、症状が治る事を期待する →→→矛盾!!
「自覚を持つ為」に森田を学習する →→→矛盾なし
森田正馬の言葉
「やりくり工夫はいらない。ただ自覚しさえすればそれで良い」
自覚を持つとは、自分を客観的に知ること →→→それによって自然と症状が治っていく。
★単純に考えると、それだと何年もの期間を要するようにも思えてしまう。それよりも手っ取り早く直接的に症状を治す方法を学びたい。そのように考えるのが神経質人間の特徴。そのような手っ取り早い方法を森田学習によって得ようとしているのではないか。しかしその方が結果として、実はかえって長い期間を要してしまう。