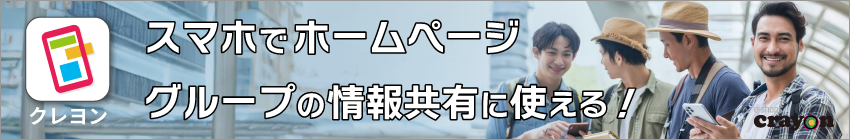-生活の発見会で森田を学んだ私が今考えている種々雑多な事など-
このHPは生活の発見会及び集談会の公式ホームページではありません。
あくまで私、真之介(しんのすけ)個人のホームページです。
発見会での症状克服過程について
以下の内容は、福岡市の集談会で学習資料として配布したところ、大変好評だったものです。発見会会員歴10年以上の男性からは「長年疑問に思っていたことの解答が、まさにここに書いてあると思った」と感想を述べました。
◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇
森田の初心者は図Aのような治り方を期待して森田学習をしているのではないでしょうか。
★画像はクリックまたはタップすれば拡大されます
発見会協力医の北西健二先生は、現代人の特徴を
「すぐに簡単に手に入る魔法の杖を欲しがる傾向」と表現しています。この場合、北西先生は薬物療法の事を「魔法の杖」と表現し、「薬物療法を受けた方がよくわかっているように、魔法の杖はないのです」と結んでいます。
『はじめての森田療法』北西健二著 講談社現代新書(p77)。
しかし、森田を学ぼうとしている人も同様に、森田に対して「魔法の杖」を求めている傾向がある、と私は思うのです。
実際には、図Bのような過程を踏まないと、ほとんどの人は治らない、と私は考えています。
★画像はクリックまたはタップすれば拡大されます
「揺り戻し(再発)」は嫌だが、あり得ない事ではないので、ある程度覚悟は必要です。
いずれにしろ、治っていく過程は一直線ではなく「行きつ戻りつ」なのです。
戻った時にガッカリして「森田は役に立たない」と思ってしまう人もいるのが、残念で仕方がありません。
「人生はそんなに簡単なものではない」と悟るべきだと思うのですが・・・・。
かつて、集談会で伴に森田学習をした人の中には「私はもう森田は充分に理解した」(でも治らない)と言い「森田は私には合わない」と発見会を去って行った人もいました。
その人は図Aのようなパターンで治る事を期待していたのだと思えるのです。(つまり森田を充分に理解していなかった)。
「飲めばすぐに効き、治る薬」(魔法の杖)というような感覚で森田に期待していた。それが叶わなかったので失望したのでしょう。
つまり図Bを経験しないまま、「森田は充分に理解した」と言って発見会から離れて行ったのです。
きっと、集談会に一度出席したのみでその後来ない人の多くは、同じような意識だったのではないかと、私は推察しています。
実は、在会年数の長いベテラン会員の中にも図Aのようなパターンで治ったと言う人も時々います。その人は、充分な自己洞察が出来ていない可能性もある、と私は思うのです。
自分がなぜ治ったのか、よく自覚できていない。あるいは、なにしろ昔の事なので細かい事は忘れてしまっている。もしくは、長く発見会に在籍しているうちに「理論学習をすれば治る」という考え方を叩き込まれ、それを疑わなくなってしまっている。
本当は「環境の変化」によって少しずつ治って行った。つまり「自然治癒」に近い形で治った人が、勘違いして「自分は図Aのパターンで治った」と主張している、というのが私の推測です。
「環境の変化による自然治癒」とは、例えばストレスの原因となった職場を退職した、転職先の新たな職場で自分を発揮できるようになった、などが例として考えられます。
あるいは、年齢を重ねて様々な人生経験を積むことにより、本当に自然治癒する人もいるかも知れません。その人は実はやはり図Bのパターンで治ったのかも知れないのですが、治った後に「自分は理論学習のお陰で治ったのだ」と理由を後付けしている可能性もなくはない、と思うのです。
森田正馬は以下のように述べています。
理屈や工夫では治らない。(神経症になった)理由がわかって、治ったというのは、それは言葉の上の説明であって、事実は、これとは逆に、治ったからその理由がわかったのである。ウナギは美味い、という話だけでは、わからないが、食ってみて初めてその美味いことがわかるのである。(中略) 単に理論がわかったから治るのではない。ある一定の実行が積んで、その体験ができて、初めて治るのである。
(『森田正馬全集第五巻』(以下「全集五巻」と呼ぶ)P395)
理屈でわかるよりも体験ができさえすれば治り、治りさえすれば、理論は容易にわかるようになるから、体験を先にする方が得策である。(全集五巻P738)
症状を克服する上で必ず通らねばならない事は職場や仕事、生活を通じての「行動・体験・経験、単に知識ではない体得」なのは言うまでもありません。
書籍による自主学習にしろ、学習会受講にしろ、理論のみで実際に体験しなければ、宝の持ち腐れになってしまいます。
例えて言えば
「自転車の乗り方を理論で学んだが、まだ実際に乗ったことはない」
「いつか、そのうち乗ってみようとは思っているのですが・・・」
というようなものです。
症状克服のポイント
以下は神経質人間の大きな特徴のひとつだと思います。
○ 待てない。焦る。せっかちで気が短い。じっと耐える事が苦手。
それに関して『HAKKEN』(会員になれば毎月送られてくる生活の発見会の機関紙。以下「発見誌」と呼びます)に書いていることを参考として引用します。
私は、森田療法を知るまでは、何か不安なこととか問題が起きるとすぐに解決しようと焦っていろいろやってしまいましたが、森田療法を知ってからは、少し待つことができるようになったと思います。
2023年11月号『わたしの体験談 メンタルヘルス岡本記念財団
第41回心の健康ビデオセミナーより
⑩自殺恐怖、不安神経症の克服体験談
さらに、以下の事も重要です
「あるがままは理解できたが、『あるがまま』になれないと悩む」人へのアドバイス
症状の苦しみをひきずりながら進むということが、いまの自分にとって「あるがまま」だということに気づいていない。あるいは、「あるがまま」を理解したと言いながら「苦しまないで前進することだ」と思い込んでいるからではなかろうか。
症状は一種のクセである。心身に根づいたクセである。新しいクセを養成するまでは、古いクセの抵抗を覚悟しなければならない。症状の苦しみをひきずりながら進むほかないのである。
2023年12月号 名文発掘
「心を強くする生きかた 自己中心からの解放」長谷川洋三
以上二つの事をもし実行できるならば、症状の悩みはやがて軽快する、と私は思います。その際、「あるがまま」とか何とか理屈を考えるのは、もうやめた方が良いと私は思うのです。理屈が先行し始めると森田学習が逆に足を引っ張っる事になります。私はそう思います。
森田の核心は何か?多くの人が、それは「あるがまま」だと言うのではないでしょうか。確かにそうだとは思います。しかし「あるがまま」は「あるがままになろうと意識すれば、それは最早あるがままではない」と言われるように禅問答のようで抽象的です。もっと具体的なもので「これぞ森田の核心だ」と言えるものはないのか?